niwa さんの日記
2015
1月
30
(金)
23:27
本文
ICFの全体図(6月23日)と最低限のICFデータ必須項目(9月9日)を参照しながら、検討しよう。
ICFの活動・参加は9領域あり、第5領域の「セルフケア」項目の内容はつぎの通りである。同時に、10月から施行される介護保険法の「認定調査票」で、ICFの「セルフケア」に該当する項目を記述する。次回の検討までに、読者のみな様も、日本の公的介護支援の中味がどのような程度と特徴があるのか。ご高察をお願いします。
1 躰を洗う:
1)水・石鹸シャワーを用いて一部を洗う
2)入浴・シャワーで全部を洗う
3)タオルやドライヤーを使って拭き乾かす
2 躰の手入れ:
1)皮膚:保湿ローションを使って、また、魚の目や胼胝(たこ)を取る
2)歯 :歯磨き、歯間清掃、義歯、矯正具を使う
3)頭髪・ひげ:整髪、ひげ剃り、刈り込み
4)手の爪:清潔に切り、磨く
5)足の爪:清潔に切り、磨く
3 排泄:
1) 排尿を調整し、適切に行う:
①尿意が分かる
②適した場所を選ぶ
③下着を取る
④姿勢をとる
⑤適切に排尿する
⑥陰部を清潔に拭く
⑦下着をつける⑧元の場所へ戻る。
2)排便を調整し、適切に行う:
①便意が分かる
②適した場所を選ぶ
③下着を取る
④姿勢をとる
⑤適切に排便する
⑥肛門と周囲を清潔に拭く
⑦下着をつける⑧元の場所へ戻る
3)生理のケア:生理のケアを適切に行う:
①生理日を予測する
②生理用品の準備
③生理用品の交換と後始末
④陰部の清潔を保つ
⑤気分をコントロールする
4 適切な衣類の選択・着脱:
1)上着:気候・社会的状況に合わせ、手際よく行う
2)ズボン:気候・社会的状況に合わせ、手際よく行う
3)履物:気候・社会的状況に合わせ、手際よく行う
4)衣服の選択:気候・社会的状況に合わせ、手際よく行う
5 食べること:
躰の状態に応じて、切る、砕くなどし、箸やフォークなどを用いて、手際よく口に運び、社会・
文化的に許される方法で食べる
6 飲むこと:
ストローやスプーン、手を用いて、手際よく口に運び、社会・文化的に許される方法で飲む
7 健康管理:
1)快適性の確保:
安楽な姿勢の保持や体温調節、室温・湿度・照明の調整、換気をして、躰のケアをする
2)食事や体調の管理:
年齢・駆る動に必要なバランスのある食事を選び、摂取し、躰力を維持する
3)健康の管理:
日々の手洗い・うがいなどの疾病予防と定期的な健康診断や、かかりつけ医の助言を
受けて、健康上のリスクを回避する
10月に始まる介護保険法の『認定調査票』で、ICFの「セルフケア」の内容に入る項目は、つぎの通りである。
1身体機能(ADL)・起居動作:
1)洗身:
浴室内で、スポンジや手拭い等に石鹸やボディソープ等を付けて全身を洗うことをいう。
2)つめ切り:
つめ切りの一連の行為のことで、「つめ切りを準備する」「切ったつめを捨てる」等を含む。
2生活機能:
1)えん下:
食物を経口より摂取する際の「えん下」(飲み込むこと)の能力である。
2)食事摂取:
食物を摂取する一連の行為のことである。通常の経口摂取の場合は、配膳後の食器から
口に入れるまでの行為のことである。また、食事摂取の介助には、経管栄養の際の注入
行為や中心静脈栄養も含まれる。「見守り等」とは、常時付き添いの必要がある「見守り」
や、行為の「確認」「指示」「声かけ」「皿の置き換え」等のことである。
3)排尿:
「排尿動作(ズボン・パンツの上げ下げ、トイレ、尿器への排尿)」「陰部の清拭」「トイレ
の水洗」「トイレやポータブルトイレ、尿器等の排尿直後の掃除」「オムツ、リハビリパン
ツ、尿とりパッドの交換」「抜去したカテーテルの後始末」の一連の行為のことである。
4)排便:
「排便動作(ズボン・パンツの上げ下げ、トイレ、排便器への排便)」「肛門の清拭」「ト
イレの水洗」「トイレやポータブルトイレ、便器等の排便直後の掃除」「オムツ、リハビリ
パンツの交換」「ストーマ(人工肛門)袋の準備、交換、後始末」の一連の行為のことである。
5)口腔清潔:
歯磨き等の一連の行為のことで、「歯ブラシやうがい用の水を用意する」「歯磨き粉を歯ブ
ラシにつける等の準備」「義歯をはずす」「うがいをする」等のことである。
6)洗顔:
洗顔の一連の行為である。一連の行為とは、「タオルの準備」「蛇口をひねる」「顔を洗う」
「タオルで拭く」「衣服の濡れの確認」等の行為をいう。また、「蒸しタオルで顔を拭く」
ことも含む。
7)整髪:
「ブラシの準備」「整髪料の準備」「髪をとかす」「ブラッシングする」等の「整髪」の一連
の行為のことである。
8)上衣の着脱:
普段使用している上衣等の着脱のことである。時候にあった衣服の選択、衣服の準備、手渡し
等、着脱までの行為は含まない。
9)ズボン等の着脱:
普段着脱しているズボン、パンツ等の着脱のことである。時候にあった衣服の選択、衣服の
準備、手渡し等、着脱までの行為は含まない。
3社会生活への適応:
1)薬の内服:
薬や水を手元に用意する、薬を口に入れる、飲み込む(水を飲ませる)という一連の行為のこ
とである。経管栄養(胃ろうを含む)などのチューブから内服薬を注入する場合も含む。
*「認定調査票」の内容は、『「認定調査員テキスト2009改訂版」の修正概要』厚生労働省老健局老人保健課 平成21年8月から引用
ICFの活動・参加は9領域あり、第5領域の「セルフケア」項目の内容はつぎの通りである。同時に、10月から施行される介護保険法の「認定調査票」で、ICFの「セルフケア」に該当する項目を記述する。次回の検討までに、読者のみな様も、日本の公的介護支援の中味がどのような程度と特徴があるのか。ご高察をお願いします。
1 躰を洗う:
1)水・石鹸シャワーを用いて一部を洗う
2)入浴・シャワーで全部を洗う
3)タオルやドライヤーを使って拭き乾かす
2 躰の手入れ:
1)皮膚:保湿ローションを使って、また、魚の目や胼胝(たこ)を取る
2)歯 :歯磨き、歯間清掃、義歯、矯正具を使う
3)頭髪・ひげ:整髪、ひげ剃り、刈り込み
4)手の爪:清潔に切り、磨く
5)足の爪:清潔に切り、磨く
3 排泄:
1) 排尿を調整し、適切に行う:
①尿意が分かる
②適した場所を選ぶ
③下着を取る
④姿勢をとる
⑤適切に排尿する
⑥陰部を清潔に拭く
⑦下着をつける⑧元の場所へ戻る。
2)排便を調整し、適切に行う:
①便意が分かる
②適した場所を選ぶ
③下着を取る
④姿勢をとる
⑤適切に排便する
⑥肛門と周囲を清潔に拭く
⑦下着をつける⑧元の場所へ戻る
3)生理のケア:生理のケアを適切に行う:
①生理日を予測する
②生理用品の準備
③生理用品の交換と後始末
④陰部の清潔を保つ
⑤気分をコントロールする
4 適切な衣類の選択・着脱:
1)上着:気候・社会的状況に合わせ、手際よく行う
2)ズボン:気候・社会的状況に合わせ、手際よく行う
3)履物:気候・社会的状況に合わせ、手際よく行う
4)衣服の選択:気候・社会的状況に合わせ、手際よく行う
5 食べること:
躰の状態に応じて、切る、砕くなどし、箸やフォークなどを用いて、手際よく口に運び、社会・
文化的に許される方法で食べる
6 飲むこと:
ストローやスプーン、手を用いて、手際よく口に運び、社会・文化的に許される方法で飲む
7 健康管理:
1)快適性の確保:
安楽な姿勢の保持や体温調節、室温・湿度・照明の調整、換気をして、躰のケアをする
2)食事や体調の管理:
年齢・駆る動に必要なバランスのある食事を選び、摂取し、躰力を維持する
3)健康の管理:
日々の手洗い・うがいなどの疾病予防と定期的な健康診断や、かかりつけ医の助言を
受けて、健康上のリスクを回避する
10月に始まる介護保険法の『認定調査票』で、ICFの「セルフケア」の内容に入る項目は、つぎの通りである。
1身体機能(ADL)・起居動作:
1)洗身:
浴室内で、スポンジや手拭い等に石鹸やボディソープ等を付けて全身を洗うことをいう。
2)つめ切り:
つめ切りの一連の行為のことで、「つめ切りを準備する」「切ったつめを捨てる」等を含む。
2生活機能:
1)えん下:
食物を経口より摂取する際の「えん下」(飲み込むこと)の能力である。
2)食事摂取:
食物を摂取する一連の行為のことである。通常の経口摂取の場合は、配膳後の食器から
口に入れるまでの行為のことである。また、食事摂取の介助には、経管栄養の際の注入
行為や中心静脈栄養も含まれる。「見守り等」とは、常時付き添いの必要がある「見守り」
や、行為の「確認」「指示」「声かけ」「皿の置き換え」等のことである。
3)排尿:
「排尿動作(ズボン・パンツの上げ下げ、トイレ、尿器への排尿)」「陰部の清拭」「トイレ
の水洗」「トイレやポータブルトイレ、尿器等の排尿直後の掃除」「オムツ、リハビリパン
ツ、尿とりパッドの交換」「抜去したカテーテルの後始末」の一連の行為のことである。
4)排便:
「排便動作(ズボン・パンツの上げ下げ、トイレ、排便器への排便)」「肛門の清拭」「ト
イレの水洗」「トイレやポータブルトイレ、便器等の排便直後の掃除」「オムツ、リハビリ
パンツの交換」「ストーマ(人工肛門)袋の準備、交換、後始末」の一連の行為のことである。
5)口腔清潔:
歯磨き等の一連の行為のことで、「歯ブラシやうがい用の水を用意する」「歯磨き粉を歯ブ
ラシにつける等の準備」「義歯をはずす」「うがいをする」等のことである。
6)洗顔:
洗顔の一連の行為である。一連の行為とは、「タオルの準備」「蛇口をひねる」「顔を洗う」
「タオルで拭く」「衣服の濡れの確認」等の行為をいう。また、「蒸しタオルで顔を拭く」
ことも含む。
7)整髪:
「ブラシの準備」「整髪料の準備」「髪をとかす」「ブラッシングする」等の「整髪」の一連
の行為のことである。
8)上衣の着脱:
普段使用している上衣等の着脱のことである。時候にあった衣服の選択、衣服の準備、手渡し
等、着脱までの行為は含まない。
9)ズボン等の着脱:
普段着脱しているズボン、パンツ等の着脱のことである。時候にあった衣服の選択、衣服の
準備、手渡し等、着脱までの行為は含まない。
3社会生活への適応:
1)薬の内服:
薬や水を手元に用意する、薬を口に入れる、飲み込む(水を飲ませる)という一連の行為のこ
とである。経管栄養(胃ろうを含む)などのチューブから内服薬を注入する場合も含む。
*「認定調査票」の内容は、『「認定調査員テキスト2009改訂版」の修正概要』厚生労働省老健局老人保健課 平成21年8月から引用
閲覧(14359)
| コメントを書く |
|---|
|
コメントを書くにはログインが必要です。 |
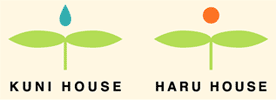

 前の日記
前の日記
